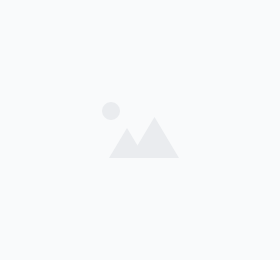この投稿は複数のページに分かれていて、各種レイアウト、画像、HTMLタグその他を含みます。
火の巻
西瓜
一
伏見桃山の城地を繞めぐっている淀川の水は、そのまま長流数里、浪華江なにわえの大坂城の石垣へも寄せていた。――で、ここら京都あたりの政治的なうごきは、微妙に大坂のほうへすぐ響き、また大坂方の一将一卒の言論も、おそろしく敏感に伏見の城へ聞えて来るらしい。
今――
摂津、山城の二ヵ国を貫くこの大河を中心にして、日本の文化は大きな激変に遭あっている。太閤たいこうの亡き後を、さながら落日の美しさのように、よけいに権威を誇示して見せている秀頼や淀君の大坂城と、関ヶ原の役から後、拍車をかけて、この伏見の城にあり、自ら戦後の経綸けいりんと大策に当たり、豊臣とよとみ文化の旧態を、根本から革あらためにかかっている徳川家康の勢威と――その二つの文化の潮流が、たとえば、河の中を往来している船にも、陸おかをゆく男女の風俗にも、流行歌はやりうたにも、職をさがしている牢人の顔つきにも、混色こんしょくしているのだった。
「どうなるんだ?」
と、人々はすぐそういう話題に興味を持つ。
「どうって、何が?」
「世の中がよ」
「変るだろう。こいつあ、はっきりしたことだ。変らない世の中なんて、そもそも、藤原道長以来、一日だってあった例ためしはねえ。――源家平家の弓取が、政権を執とるようになってからは猶なおさらそいつが早くなった」
「つまり、また戦いくさか」
「こうなっちまったものを、今さら、戦のない方へ、世の中を向け直そうとしても、力に及ぶまい」
「大坂でも、諸国の牢人衆へ、手をまわしているらしいな」
「……だろうな、大きな声ではいえねえが、徳川様だって、南蛮船から銃や弾薬たまぐすりをしこたま買いこんでいるというし」
「それでいて――大御所様のお孫の千姫を、秀頼公の嫁君にやっているのはどういうものだろ?」
「天下様のなさることは、みな聖賢の道だろうから、下人げにんにはわからねえさ」
石は焼けていた。河の水は沸いている。もう秋は立っているのだが、暑さはこの夏の土用にも勝まさって酷きびしい。
淀の京橋口の柳はだらりと白っぽく萎なえている。気の狂ったような油蝉あぶらぜみが一匹、川を横ぎって町屋の中へ突き当ってゆく。その町も晩の灯の色はどこへか失って、灰を浴びたような板屋根が乾き上がっているのだった。橋の上下かみしもには、無数の石船がつながれていて、河の中も石、陸おかも石、どこを見まわしても石だらけなのである。
その石も皆、畳二枚以上の巨おおきなものが多かった。焼けきった石の上に、石曳いしひきの労働者たちは、無感覚に寝そべったり腰かけたり仰向けに転がったりしている。ちょうど今が、昼飯刻どきでその後の半刻休みを楽しんでいるのであろう。そこらに材木をおろしている牛車の牛も涎よだれをたらして、満身に蠅はえを集めてじっとしている。
伏見城の修築だった。
いつのまにか、世の人々に「大御所」と呼ばしめている家康がここに滞在しているからではない。城普請しろぶしんは、徳川の戦後政策の一つだった。
譜代大名ふだいだいみょうの心を弛緩しかんさせないために。――また、外様とざま大名の蓄力を経済的にそれへ消耗させてしまうために。
もう一つの理由は、一般民に、とにかく徳川政策を謳歌おうかさせるためには、土木の工を各地に起して、下層民へ金をこぼしてやるに限る。
今、城普請は全国的に着手されていた。その大規模なものだけでも、江戸城、名古屋城、駿府城、越後高田城、彦根城、亀山城、大津城――等々々。
二
この伏見城の土木へ日稼ひかせぎに来る労働者の数だけでも、千人に近かった。その多くは、新曲輪しんぐるわの石垣工事にかかっているのである。伏見町はそのせいで、急に、売女ばいたと馬蠅うまばえと物売りが殖ふえ、
「大御所様景気や」
と、徳川政策を謳歌した。
その上、
「もし戦争になれば」
と、町人たちは、機と利を察して、思惑に熱していた。社会事象のことごとくを、そろばん珠にのせて、
「儲もうけるのはここだ」
無言のうちに、商品は活溌にうごいた。その大部分が、軍需品であることはいうまでもない。
もう庶民の頭には、太閤時代の文化をなつかしむよりも、大御所政策の目さきのいい方へ心酔しかけていた。司権者は誰でもいいのである。自分たちの小さな慾望のうちで、生活の満足ができればそれで苦情がないのだ。
家康は、そういう愚民心理を、裏切らなかった。子どもへ菓子を撒まいてやるより易々いいたる問題であったろう。それも徳川家の金でするのではない。栄養過多な外様大名に課役させて、程よく、彼らの力をも減殺させながら効果を挙げてゆく。
そうした都市政策の一方、大御所政治は、農村に対しても、従来の放漫な切り取り徴発や、国持くにもちまかせを許さなかった。徳川式の封建政策をぽつぽつ布しきはじめていた。
それには、
(民をして政治を知らしむなかれ、政治にたよらせよ)
という主義から、
(百姓は、飢えぬほどにして、気ままもさせぬが、百姓への慈悲なり)
と、施政の方策をさずけて、徳川中心の永遠の計にかかっていた。
それはやがて、大名にも、町人にも、同じようにかかって来て、孫子の代まで、身うごきのならない手かせ足かせとなる封建統制の前提であったが、そういう百年先のことまでは、誰も考えなかった。いや、城普請しろぶしんの石揚げや石曳きに稼ぎに来ている労働者などは、明日あしたのことさえ、思っていないのである。
昼飯をたべれば、
「はやく晩になれ」
と祈るのが、いっぱいな慾念だった。
それでも時節がら、
「戦争になるか」
「なれば何日いつ頃?」
などと、時局談は、いっぱし熾さかんだったが、その心理には、
「戦争になったって、こちとらは、これ以上、悪くなりようがねえ」
という気持があるからで、ほんとにこの時局を憂うれいたり、平和の岐点をじっと案じて、どの方へ曲がるのが国と民のためだろうなどと考えているのでは決してないのである。
「――西瓜すいかいらんか」
いつも昼休みに来る百姓娘が、西瓜の籠を抱えて触れて来た。石の蔭で、銭ぜにの裏表を伏せて、博戯ばくちをしていた人足の群れで、二つ売れた。
「こちらの衆は、西瓜どうや。西瓜買うてくれなはらんか」
と、群れから群れへ唄ってくると、
「べら棒め、銭がねえや」
「ただなら食ってやる」
そんな声ばかりだった。
すると、たった一人ぽち、青白い顔をして、石と石のあいだに倚よりかかって膝を抱えていた石曳きの若い労働者が、
「西瓜か」
と、力のない眼をあげた。
痩せて――眼がくぼんで――日に焦やけて、すっかり変ってしまったが、その石曳いしひきは、本位田又八ほんいでんまたはちだった。
三
又八は、土のついた青銭を、掌のうえでかぞえた。西瓜売りにわたして一個の西瓜と交換した。それを抱え込むと、またしばらく、石に倚りかかったまま、ぐんなり俯向うつむいているのである。
「げ……げ……」
突然、片手をつくと、草の中へ牛みたいに唾液だえきを吐いた。西瓜は膝から転がり出している。それを取ろうとする気力もないし、食べようという気で買ったわけでもないらしいのだ。
「…………」
にぶい眼で、西瓜をながめていた。眼は虚無の玉みたいに何の意力も希望もたたえていない。呼吸いきをすると肩ばかりうごいた。
「……畜生」
呪う者ばかりが頭脳あたまへ映ってくる。お甲こうの白い顔であり、武蔵たけぞうのすがたであった。今の逆境へ落ちて来た過去を振顧ふりかえると、武蔵がなかったらと思い、お甲に会わなかったらと彼はつい思う。
過あやまちの一歩は、関ヶ原の戦いくさの時だ。次に、お甲の誘惑だ。あの二つのことさえなかったら、自分は今も、故郷ふるさとにいたろう。そして本位田家の当主になって、美しい嫁をもち、村の人々から、羨望せんぼうされる身でいられたに違いない。
「お通つうは、怨んでいるだろうなあ……。どうしているか」
彼の今の生活は、彼女を空想することだけが慰めだった。お甲という女の性質がよくわかってからは、お甲と同棲しているうちから、心はお通へもどっていたのだった。やがてあの「よもぎの寮」と呼ぶお甲の家を、ていよく突き出されたような形で出てしまってからは、よけいにお通を思うことが多かった。
その後また、よく洛内らくないの侍たちの間で噂にのぼる宮本武蔵なる新進の剣士が、むかし友達の「武蔵たけぞう」であることを知ると、又八はじっとしていられなかった。
(よしっ、俺だって)
彼は酒をやめた。遊惰な悪習を蹴とばした。そして次の生活へかかりかけた。
(お甲のやつにも、見返してやるぞ。――見ていやがれ)
だが、さしずめ適当な職業は見つからなかった。五年も世間を見ずに、年上の女に養われて来た不覚のほどが、はっきり身に沁みて分ったが、遅かった。
(いや、遅かあない。まだ二十二だ。どんなことをしたって……)
と、これは誰にでも起せる程度の興奮だったが、又八としては、眼をつぶって運命の断層をとび越えるような悲壮をもって、この伏見城の土木へ働きに出たのだった。そしてこの夏から秋までの炎天下で、自分でもよく続いたと思うほど労働をつづけていた。
(おれも、一かどの男になってみせる。武蔵のやる芸ぐらい、俺に出来ない法はない。いや、今にあいつを尻目にかけて、出世してみせてやる。その時には、お甲にも黙って復讐できるのだ。見ていろここ十年ばかりに)
だが――と彼はふと思うのだった――十年経ったら、お通は幾歳いくつになるだろうと。
武蔵や自分よりも、彼女は一ツ年下だ。すると今から十年経つうちには、もう三十を一つこえてしまう。
(それまで、お通が、独り身で待っているかしら?)
故郷のその後の消息は何も知らない又八だった。そう考えると、十年では遠すぎる、少なくもここ五、六年のうちだ。なんとしても身を立てて、故郷へ行き、お通に詫びて、お通を迎え取らなければならない。
「そうだ……五年か、六年のうちに」
西瓜を見ている眼に、やや光が出てきた。すると、巨おおきな石の向う側から、仲間の一人が、肱ひじを乗せていった。
「おい又八、何をひとりでぶつぶついってるんだ。……オヤ、ばかに青い面つらして、げんなりしているじゃねえか。どうしたんだ、腐った西瓜でも喰らって、腹でも下痢くだしたのか」